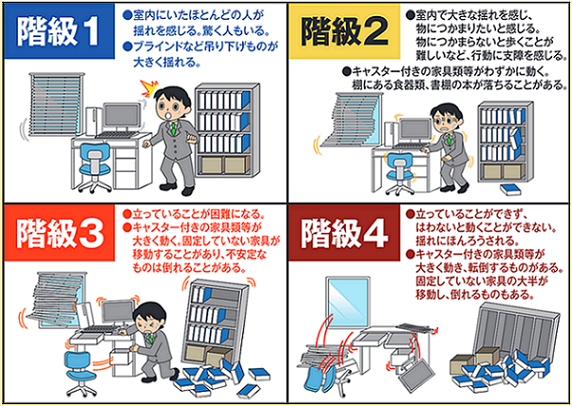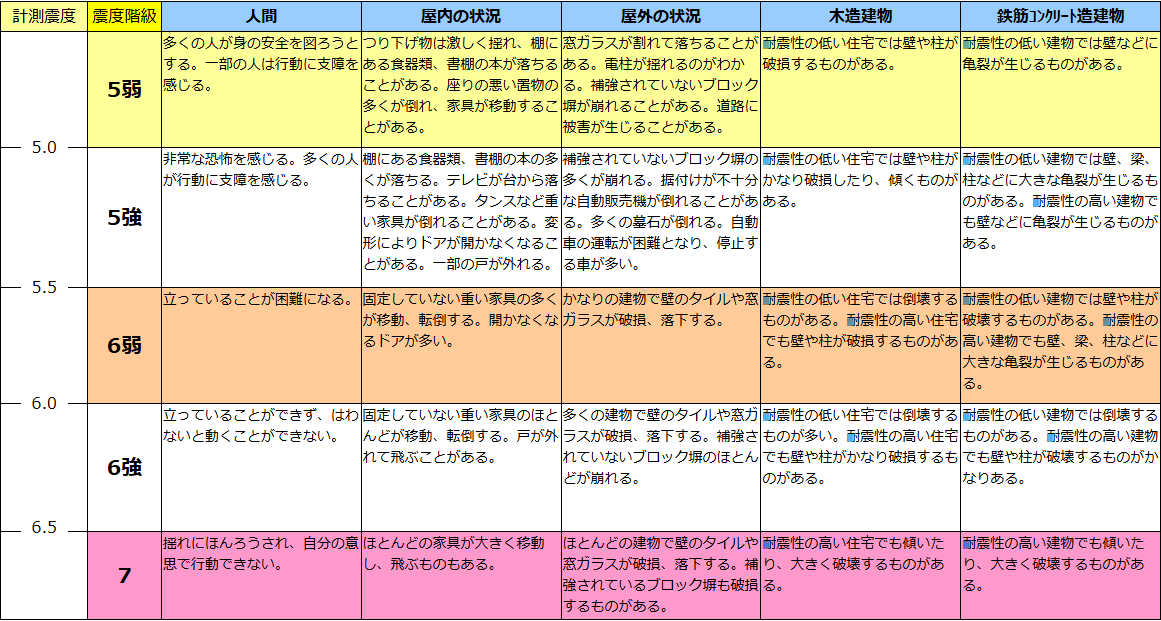業種・業界別の事業継続計画(BCP)のススメ<その2>
前回はBCPの入門的な意味も含めて『内閣府のBCP』をご紹介しました。
今回は「国土交通省のBCP」をご紹介したいと思います。
国土交通省は「国土の総合的かつ体系的な利用、開発および保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、気象業務の発展並びに海上の安全および治安の確保などを担う官庁」となっており、監督する業界としましては
- 建設業
- 不動産業
- 陸海空の運輸、運送業や物流業(倉庫業等)
- 道路や空港、港湾等の公的なインフラ関連
- 自動車関連
等が一般的に分かりやすいかと思います。
また、社会インフラの中で上下水道や道の駅は国土交通省の管轄となっています。
国土交通省として、全ての業種業界へ事業継続(BCP)を求めている訳ではありませんが、公開されているBCPについてのガイドラインや認証制度をご紹介します。
建設業向けBCP
建設業では企業としての存続(災害時の事業継続)だけでなく、公共インフラの復旧・復興を担う事もあり、BCPの認証制度が設けられています。
この認証は更新制で、有効期間は2~3年となっています。
申請手続きは、企業の所在地に応じた地方整備局が窓口となります。
https://www.ktr.mlit.go.jp/bousai/index00000044.html
(国土交通省・関東地方整備局:建設会社における災害時の事業継続力認定)
この認証の注意点としまして、申込書類に虚偽記載等が判明した場合、不適合通知が発行され「1年間の申込不受理」のペナルティが課されます。
公的な認証を目指してはいないがBCPを策定したい、という場合は次のようなページも参考になります。
https://www.mlit.go.jp/common/000032865.pdf
(国土交通省・関東地方整備局:建設会社のための災害時の事業継続簡易ガイド)
https://www.nikkenren.com/publication/detail.html
(一般社団法人 日本建設業連合会:建設BCPガイドライン)
物流業向けBCP
物流業では業務の流れの中で複数の事業者が存在し立場も異なるため、必要とされるBCPが異なる事から複数の検討会・ガイドラインが存在します。
物流の例:荷主(発荷主)~輸送事業者・保管事業者等~配送先(着荷主)
https://www.mlit.go.jp/common/001087785.pdf
(国土交通省:荷主と物流事業者が連携した BCP策定のためのガイドライン)
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001601839.pdf
(国土交通省:多様な災害に対応したBCP策定ガイドライン)
民間の団体(倉庫業)からも下記のようなBCPの情報が公開されています。
※BCP作成のてびき・全社BCPモデル・IT部門BCPモデルが無料公開されています。
https://www.nissokyo.or.jp/bcp/
(一般社団法人 日本倉庫協会:事業継続計画書) ※一部会員専用となっております。
道の駅のBCP
道の駅は国土交通省に登録された施設で、自治体主導の運営が一般的ですが、管理や営業を民間事業者が行っているケースもあります。
BCP策定のためのガイドライン案が公開されています。
https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/michi-no-eki_third-stage/pdf04/04.pdf
(国土交通省:「道の駅」におけるBCPガイドライン(案)について)
今回ご紹介しました各種情報は民間企業を想定してピックアップしておりますが、国土交通省は地方公共団体の活動にも深く関わっており、下水道事業向けのBCP・空港向けBCP・港湾向けBCP等も公開されています。
公共事業に関わっている企業の場合は国土交通省のWebページより該当する分野を検索しますと、自治体に求められているBCP等の情報が得られる場合があります。
国土交通省は管轄する業種業界が広いので、BCPにおいても1つに絞り込む/ガイドラインを統一するといった事が困難となっています。BCPを作成する際は、自社の業種業界に合ったものを探すところから始めていただくと良いと思います。
また、公的な役割(災害時の非常対応、復旧や復興等)を担っておられる企業/団体の場合は、自治体や公的な団体のBCPについても知っていただくと、想定される連携体制や求められる対応にもつながることかと思います。